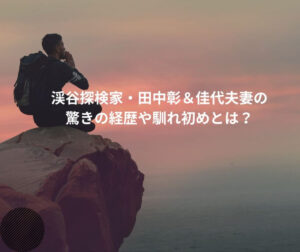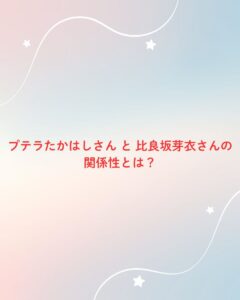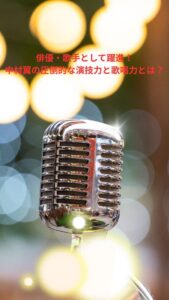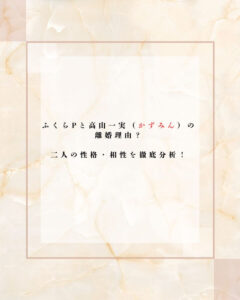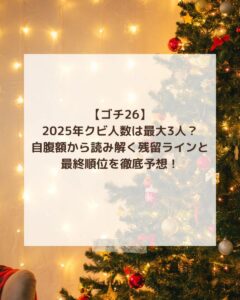小泉進次郎氏は、環境問題や地方創生、社会保障改革など、多岐にわたる分野から、これまでに独自のメッセージを発信してきました。
過去の発言や政策、そしてそこから推測される方向性について触れていきます。
※この記事はあくまでも筆者の憶測や推測です
1. 小泉進次郎氏の政治活動における主要発言と政策
9/12(金)の #報道1930 は...
— BS-TBS「報道1930」 (@bstbs1930) September 12, 2025
『#小泉進次郎農水相 が生出演
#総裁選挙 と農政の未来は..』
【ゲスト】
#小泉進次郎 @shinjirokoiz
(農林水産大臣)#後藤謙次
(ジャーナリスト)
詳しくはHPへ👇 https://t.co/7JlCX9cXTv
インスタグラムはこちら👇https://t.co/KRUF7PAo3Z… pic.twitter.com/jKBe01jrDX
引用元/@bstbs1930 Xより
1-1. 環境・気候変動政策(2019年9月〜2021年10月)

小泉進次郎氏は環境大臣時代に、カーボンニュートラル政策を積極的に推進しました。
環境省での記者会見では「2050年カーボンニュートラル宣言を総理が行ったことで、企業、スポーツ、自治体など、とにかく再生可能エネルギー、脱炭素に向かっていく契機を生んだ」と述べています。
具体的な政策実績は以下の通りです。
- レジ袋有料化の推進
- プラスチック削減政策の積極展開
- 46%温室効果ガス削減目標の推進
(カーボンニュートラル)
レジ袋有料化の推進は、2019年に環境大臣としての任期中に実施されています。
プラスチックごみの削減を目的としており、2020年7月から全国的に施行されました。
具体的には、レジ袋の無料配布を禁止し、消費者に対して有料での提供を義務付ける形での実施です。
小泉氏は、「プラスチックへの問題意識を持ってもらうこと」と述べており、単なるごみ削減だけでなく、環境問題への関心を促すことが重要だと考えていました。
この政策の結果、レジ袋の使用量は約70~80%減少したと報告されています。
しかし、批判も多く、特に「実質的な値上げ」として受け取られることが多かったため、消費者からの反発もありました。
また、レジ袋の有料化が他のプラスチック製品の有料化へと波及する懸念も示されています。
小泉氏のレジ袋有料化政策は、環境保護の観点から支持される一方で、実効性や必要性について疑問を呈する声も多くありました。
特に、レジ袋がプラスチックごみに占める割合はそれほど大きくないとの指摘もあり、政策の効果に対する科学的根拠が不足しているとの見方や批判もあるようです。
46%の温室効果ガス削減目標の推進では、菅義偉首相が国際的な気候変動サミットで発表したもので、特にアメリカとの関係を考慮した結果とも言われています。
小泉氏は、環境大臣としてこの目標の重要性を強調し、政府の意欲的な姿勢を示すためのものであると述べました。
また、目標に関する発言の中で「46という数字がおぼろげながら浮かんできた」と述べ、これがメディアで物議を醸しましています。
この発言は、目標の具体的な根拠が不明確であるとの批判を招き、彼は後に「発言が切り取られている」と釈明しました。
賛否はありますが、小泉氏が環境大臣として、メガソーラー等の再エネ発電所の設置は、温室効果ガス削減目標の推進の一つと言えるでしょう。
1-2. 農業改革への挑戦(2015年~2017年)

農林中金改革と補助金依存農業からの脱却
小泉進次郎氏は閣僚になる前の自民党農林部会長時代には、抜本的な農業構造改革を提言しています。
農林中金改革において、総資産100兆円の巨大金融機関でありながら、農業融資が全体の0.1%しかない問題を指摘し、「年間の国家予算に匹敵する額が農業のために使われないのなら、他の金融機関が運用した方がいい」と、小泉氏は農協(JA)に対して述べられていました。
しかし、これには農家への融資は農協(JA)などが行っていると言及し、農林中金は農協の事業の赤字を補助し、日本の農業を支える役割であると反論しています。
小泉氏の発言は、日本の農業が抱える非効率なコスト構造を問題視し、その原因が農協(JA)の体制にあると追及しているようです。
具体的には、「肥料の種類とコスト」「ダンボールの強制」「農機具の価格」の3つが挙げられます。
これらの3つが、農協の生産コスト上昇に繋がっていることから、農家にとって不必要な負担であり、日本の農家がわざわざ海外で購入しているという事実を小泉氏は指摘されているようです。
また、小泉氏は「農業は弱い立場であるから守らなければいけない。そのために補助金が必要だ」という発想からの転換を主張しています。
彼は競争力強化と市場メカニズム重視の「稼げる農業」への転換を提唱しているようです。
しかしながら、補助金依存農業からの脱却を目指しているという取り組みは、一つの懸念もあります。
それは、小泉氏の農協改革が単なる国内的な問題解決策ではなく、在日米国商工会議所(ACCJ)などのアメリカ側からの要求と密接に関連している可能性があるかもしれないからです。
具体的には、以下の点が挙げられます。
・農協の解体・株式会社化
・農協の政治力の排除
農協の解体・株式会社化は、農協を農業部門と金融部門に分け、金融部門を金融庁の管理下に置くことで、日本の巨大な金融資産(JAバンクやJA共済)を、外資を含む他の金融機関と「平等な競争環境」に置くことを目指すものです。
これにより、アメリカの金融機関が日本の巨大な農業市場に参入することになります。
農協の政治力の排除は、農協が持つ政策提言機能や政治的影響力を弱めることで、日本の農政全体がアメリカの意向に沿いやすくなるという見方も示されています。
この見解は、小泉氏の改革が日本の農業の効率化という表向きの目的だけでなく、裏にアメリカの市場開放要求が潜んでいるという、陰謀論的な側面も含まれていることに注意が必要です。
ただし、日米間の経済交渉や規制改革において、アメリカ側が日本の特定の産業に市場開放を求めることは、しばしば行われてきたため、このような見方は一定の説得力を持つ場合もあります。
ただ、外資になるかもしれないことを考慮すると、国民の懸念は一層に深まる可能性があるかもしれません。
※農協の解体・株式会社化と農協の政治力の排除は、あくまでも憶測や推測です
農林水産大臣としての取り組み(2025年5月〜)
20日(水)18:58~
— 深層NEWS【公式】BS日テレ月~金よる6時58分生放送 (@sinso_news) August 20, 2025
値下がりしていたコメ価格が上昇している。政府は今月末まで売り切るように求めていた随意契約による備蓄米を来月以降も販売を認める方向で最終調整しているという。令和のコメ騒動、解決への舵取りを担う小泉農林水産相に対策を聞く。そして次の首相へ待望論も根強い中、本人の意欲は pic.twitter.com/rOjBL9n0Hw
引用元/@sinso_news Xより
小泉進次郎氏の農林水産大臣としての取り組みは、以下の通りです。
- 「5kg2000円を目指す」という具体的な価格目標を設定
- 政府備蓄米の随意契約による安価放出を断行
- コメ卸業者の高利益(500%増)を批判し、流通構造改革に着手
小泉氏は、政府備蓄米を5kgあたり2000円で提供することを目指しています。
この価格設定は、消費者に安価で米を供給することを目的としており、特に米の価格が高騰している現状を受けたものです。
彼は、備蓄米の放出を通じて、消費者が手に取りやすい価格で米を購入できるようにする意向を示しています。
小泉氏は、備蓄米の放出方法を競争入札から随意契約に変更することを決定し、これにより、より迅速かつ柔軟に米を市場に供給できるようにし、価格の安定を図る狙いがあります。
具体的には、2025年5月28日から予定されていた入札を中止し、随意契約による売渡しを行うことを発表していました。
さらに、彼は、コメ卸業者の利益が前年比で500%増加していることを指摘し、流通構造の改革に着手する意向を示しました。
彼は、卸業者の高利益が市場における価格高騰の一因であるとし、流通の透明性を高める必要があると強調しています。
この発言は、卸業者からの反発を招く一方で、流通業界の改革を促進する契機となる可能性もありますが、一部の田舎地方では個人的な声として、備蓄米をほとんど見かけないという声があり、成果を疑問視している方もおられるようです。
この政策は、筆者の個人的な見解ですが、流通網が発達している関東地方とその近隣地域に限定的な効果だったのではないでしょうか?
2. 過去の類似事例から見る若い首相との比較(戦後最年少の首相)

2025年10月4日に自民党総裁選が前倒しされるという事で、小泉進次郎氏にも、注目が集まっています。
まだ、小泉氏は首相に就任していませんが、過去の類似事例から若くして首相となった人物と比較してみました。
戦後最年少の首相以外だと、44歳で就任した伊藤博文と45歳で就任した近衛文麿がいますが、ここは省き、昭和の戦後最年少の首相と比較します。
戦後最年少の首相には、以下の2人がいます。
主な事績についても簡潔に記載しておきます。
田中角栄氏(54歳で首相就任、1972年)
- 日本列島改造論による国土開発政策
- 強いリーダーシップと実行力
- 最終的にロッキード事件で失脚
安倍晋三氏(52歳で首相就任、2006年)
- 戦後最年少記録を更新
- 第一次政権は1年で終了(健康問題で辞任)
- 第二次政権では長期安定政権を実現
お二方とも、日本の戦後史に大きな足跡を残した首相として知られています。
2-1. 田中角栄氏について

田中角栄氏は、1972年7月7日に54歳で首相に就任しています。
彼は1972年6月「日本列島改造論」を提唱し、これを基に国土開発政策を進めました。
この論文は、全国のインフラ整備を通じて地域間の格差を解消し、経済成長を促進することを目的としています。
具体的には、高速道路や新幹線の整備、地方の産業振興を目指し、都市と地方の均衡ある発展を図るものです。
田中氏は「コンピューター付きブルドーザー」と称されるほどの強いリーダーシップと実行力を持っていました。
彼は迅速な決断を下し、実行に移す能力に優れており、特に官僚との連携を重視。
彼の政治スタイルは、即断即決を基本とし、効率的な政務運営を行っています。
しかし、田中氏の政権はロッキード事件によって大きな打撃を受けており、この事件では、彼が米国の航空機メーカーから賄賂を受け取ったとされ、1974年に辞任を余儀なくされました。
事件は日本の政治史において重要な転機となり、田中氏はその後、逮捕され有罪判決となります。
これらの要素が田中角栄氏の政治的キャリアを形作り、彼の影響力を示しています。
2-2. 安倍晋三氏について
昨日「交詢社オープンフォーラム」で「緊張する台湾海峡情勢に日本はどう対応すべきか」について講演しました。https://t.co/X8XdbgYJB4
— 安倍晋三 (@AbeShinzo) June 5, 2022
引用元/@AbeShinzo Xより
安倍晋三氏は2006年9月26日に52歳で首相に就任し、戦後最年少の首相としての記録を更新しました。
この就任は、彼が自民党の総裁選で勝利した結果です。
安倍氏の第一次政権は、自身の健康問題により2007年にわずか1年で終了しています。
彼は持病の潰瘍性大腸炎が悪化し、これが辞任の理由となりました。
2012年に再び首相に就任した安倍氏は、第二次政権を2012年から2020年まで続け、憲政史上最長の連続在職日数を記録しています。
この政権下では、アベノミクスと呼ばれる経済政策を推進し、国内外での影響力を強化しました。
これらの事績が安倍晋三氏の政治的キャリアを形作り、彼の影響力を示しています。
2-3. 小泉進次郎氏:二人の首相から比較しての共通点?

小泉進次郎氏と田中角栄氏の共通点
小泉進次郎氏の政策と田中角栄氏の政策の共通点は以下のことが考えられます。
1. 地方創生と国土開発
2. 環境政策への取り組み
3. 大衆へのアピール
田中氏は「日本列島改造論」を通じて、地方の活性化と国土の均衡ある発展を目指しており、彼の政策は、都市と地方の格差を解消し、全国的なインフラ整備を進めるものでした。
小泉氏も、地方創生を重要な政策課題として掲げています。
彼は、人口減少や少子高齢化といった現代の課題に対処するため、地方の活性化を図る必要性を強調しています。
環境政策への取り組みでは、田中氏は、エネルギー政策や環境問題にも関心を持ち、原発政策を進めるなどしていました。
特に第1次石油危機が発生した頃は、中東地域以外からのエネルギーの直接確保に努めていることからも、彼が関心を持っていることが分かります。
彼の政策は、経済成長と環境保護の両立を目指すものでした。
小泉氏も環境大臣として、気候変動対策や持続可能な社会の実現に向けた政策を推進しており、特に、プラスチックごみ削減や再生可能エネルギーの導入を重視しています。
大衆へのアピールでは、両者ともに、国民に対する強いアピール力を持っています。
田中角栄氏は「今太閤」と称されるほどの人気を誇り、庶民的な感覚を大切にした政治を展開しました。
小泉進次郎氏も、若者や女性を中心に支持を集めており、親しみやすいキャラクターで知られています。
これらの共通点から、両者は異なる時代背景においても、国民の期待に応える政策を展開していると言えます。
しかし、個人的な見解としては、田中角栄氏が持つ政治力や大衆へのアピール力は、奇抜なパフォーマンスも相まって、進次郎氏には見劣りする点があるように感じられます。
小泉進次郎氏の政策と安倍晋三氏の政策の共通点
小泉進次郎氏の政策と安倍晋三氏の政策の共通点は、以下のことが考えられます。
1. 経済政策
2. 環境政策
3. 外交政策
両者は経済成長を重視しており、特に企業の賃金引き上げや女性の労働参加を促進する政策を支持しています。
安倍氏は「アベノミクス」として知られる経済政策を推進し、デフレ脱却を目指しました。
小泉氏も、経済の活性化に向けた施策を提案しており、特に農業や社会保障に関する政策に力を入れています。
環境政策では、安倍氏は、原発再稼働を進める一方で、環境問題にも配慮した政策を展開しました。
小泉氏は環境大臣として、プラスチックごみ削減や再生可能エネルギーの導入を強調しています。
両者ともに、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを行っていますが、原発に対するスタンスには違いがあります。
外交政策では、安倍氏は、アメリカとの同盟関係を重視し、国際的な安全保障を強化するための政策を推進しました。
小泉氏も、国際的な問題に対して積極的な姿勢を示しており、特に環境問題において国際的な協力を重視しています。
これらの共通点から、両者は異なる時代背景においても、経済成長や環境問題、外交政策において類似したアプローチを取っていることがわかります。
しかし、小泉進次郎氏と安倍晋三氏を比較しても、田中角栄氏と同様に小泉氏は、安倍氏の政治力には見劣りしてしまうと個人的には感じます。
小泉氏は第4次安倍内閣の第2次改造で環境大臣を務めていましたから、安倍氏の政治力と比較して見劣りを感じるのは、安倍氏の業績が大き過ぎて、そのように感じてしまうのかもしれません。
仮に小泉氏が、2025年10月の総裁選で選任され、首相に就任した場合は、戦後最年少の首相として、安倍氏の更新記録を超えることとなるでしょう。
3. 小泉進次郎氏の多角的評価(ポジティブ面とネガティブ面)
閣議後の定例記者会見@農林水産省。「地域計画」について新たな情報を発表しました。詳しくはプレスリリースをご覧ください。https://t.co/6wWl38DCbq pic.twitter.com/hpMDegZJvk
— 小泉進次郎 (@shinjirokoiz) September 9, 2025
引用元/@shinjirokoiz Xより
小泉進次郎氏の多角的評価として、ポジティブ面とネガティブ面を見ていきます。
3-1. ポジティブな側面
小泉氏のポジティブな側面には、若さゆえのリーダーシップへの期待があります。
具体的には以下の通りです。
- デジタルネイティブ世代に対しての情報発信力
- 国際的な環境政策での先進的取り組み
- 既得権益との対決姿勢
(農協改革、流通改革) - 具体的な数値目標設定
(46%削減、5kg 2000円など)
いくつかは既に政策で触れていますが、それも含めて記載しておきます。
デジタルネイティブ世代に対しての情報発信力
小泉氏はデジタルネイティブ世代ではありませんが、SNSを活用した情報発信に長けています。
彼は、迅速かつ効果的に自らの考えや政策を広める能力を持ち、特に若い世代とのコミュニケーションにおいて強みを発揮しています。
彼は情報をスピーディに発信し、柔軟な思想を持つことが特徴です。
現在では小泉氏に限らず、SNSを活用した情報発信する政治家も増えていることから、あまり珍しいことではないかもしれません。
国際的な環境政策での先進的取り組み
小泉氏の国際的な環境政策は先ほどにも触れていますが、特に、温室効果ガスの46%削減目標を掲げるなど、具体的な数値目標を設定し、国際的な枠組みの中で日本の役割を強調しています。
彼の政策は、数値目標を設定したことに賛否はありますが、持続可能な社会の実現に向けた先進的な取り組みとして一部では評価されています。
既得権益との対決姿勢
小泉氏は、農協改革や流通改革など、既得権益に対する挑戦を公言しています。
彼は、古い体制や利権にとらわれず、新しい改革を進める姿勢を示しており、これが若い世代からの支持を集める要因となっているようです。
特に、農業や流通における改革は、彼のリーダーシップの重要な側面です。
具体的な数値目標設定
小泉氏は、政策において具体的な数値目標を設定することを重視しています。
例えば、先ほどの温室効果ガスの46%削減や、米の価格を5kgあたり2000円にするという目標は、彼の政策の具体性を示しています。
このような明確な目標設定は、政策の実行可能性を高め、国民に対する信頼感を醸成することに繋がるでしょう。
彼の政策実行力は、環境大臣時代に培ったカーボンニュートラルの推進、農水大臣就任直後の迅速な備蓄米放出決断などがあります。
備蓄米放出について、東洋経済の記事には「小泉大臣やるじゃん」との評価もあるようです。
3-2. ネガティブな側面・今後の課題
小泉氏には、ネガティブな側面もあります。
経験不足と言われたり、政策の目的・手段が複雑で実現の可能性が疑問視されていることもあります。
具体的には、以下の通りです。
- 「進次郎構文」と呼ばれる意味不明な発言パターン
- 「無知発言連発」との厳しい批判
- 具体的政策の詳細設計や実現可能性への疑問
これらについて記載しておきます。
「進次郎構文」と呼ばれる意味不明な発言パターン
小泉氏の発言には「進次郎構文」と呼ばれる独特の言い回しがあり、これは同義語の反復やトートロジー(重言)を含むことが特徴です。
例えば、「このプレゼント、頂き物なんです」というように、当たり前のことをあたかも特別なことのように表現することが多く、情報としての機能を果たしていないと批判されています。
これは、小泉氏の独特な個性と言えるのかもしれませんが、よくメディアでも見かける光景のため、ご存知な方も多いのではないでしょうか。
「無知発言連発」の批判と「過去の発言への懸念」について
日刊ゲンダイによると、小泉氏の発言を「無知発言」として厳しく批判しているようです。
具体的には、農業や環境政策に関する基本的な知識が不足しているとされ、例えば「レンタルとリースの違いも分からない」といった指摘がなされています。
これにより、彼の知的レベルや政策の実現可能性に対する疑問が生じているとのことです。
また、小泉氏は過去の発言への懸念もあります。
特に「セクシー発言」と「ステーキ毎日発言」が注目され、批判を受けているとのことです。
2つについても触れておきます。
小泉氏は2019年9月、ニューヨークでの国連気候行動サミットにおいて、「気候変動問題に取り組むことは楽しく、クールで、セクシーであるべきだ」と発言しました。
この発言は、同席していた国連気候変動枠組条約のクリスティアナ・フィゲレス前事務局長の言葉を引用したものでしたが、日本のメディアでは「セクシー」という言葉が性的な意味合いを持つため、批判が集中したのです。
この発言は、文脈を理解しない批判が続き、特に日本のメディアは表面的な報道に終始したと指摘されています。
アメリカの友人たちからは、「なぜ問題になるのか理解できない」との声も上がり、文化的な誤解が背景にあるとされているとのことです。
小泉氏自身は、発言の意図を「気候変動問題を魅力的に伝えることが重要」と説明していますが、具体的な政策についての質問には答えられなかったことも批判の一因となっています。
「ステーキ毎日発言」については、同じく2019年、ニューヨークでの国連会議に参加中、小泉氏は「毎日でもステーキを食べたい」と発言しました。
この発言は、環境大臣としての立場から見て不適切であるとの批判を受けているようです。
特に、環境問題に対する配慮が欠けているとの指摘が多く、肉食が環境に与える影響を考慮しない発言として問題視されました。
この発言もまた、文脈を無視した批判が多く、特に日本のメディアでは「環境大臣としての自覚がない」といった声が上がっています。
小泉氏は、環境問題に対する意識を高めるための発言だったと主張していますが、実際にはその意図が伝わらず、逆に批判を招く結果となったようです。
これらの発言は、小泉進次郎氏のリーダーシップに対する期待と同時に、彼の発言の軽さや文脈理解の不足が問題視される要因となっています。
ただ、「セクシー発言」と「ステーキ毎日発言」について、個人的には日本のメディアのニュアンスが度を過ぎていると感じます。
「セクシー発言」は、アメリカの友人たちから言われる通り、「なぜ問題になるのか理解できない」という気持ちが分かる気がするのです。
文化的な誤解が背景にあるというのは、妥当な意見であると感じました。
「ステーキ毎日発言」についても、これはアメリカの国民目線で見ると妥当な声だと思うのです。
アメリカの主食は肉食ですから、「ステーキ毎日発言」は、アメリカでは普通の事ではないでしょうか。
要は肉食が環境に与える影響について、今後どうしていくことが重要であるかが課題です。
別に、小泉氏を擁護するという意図はありませんが、具体的な政策についての質問には答えられなかったのは致命的だったのかもしれないですね。
日本のメディアは、少々叩きすぎと感じますから、もう少し考慮すべきではないでしょうかね?
具体的政策の詳細設計や実現可能性への疑問
小泉氏の政策には、具体的な数値目標が設定されているものの、その詳細設計や実現可能性については疑問が残ります。
例えば、何度も記載していますが、温室効果ガスの46%削減や米の価格を5kgあたり2000円にするという目標は掲げられていますが、これを実現するための具体的な手段や計画が不明瞭であるとの指摘があります。
政策の実行に向けた具体的なアプローチが不足しているため、実現可能性が疑問視されることが多いです。
また、小泉氏は現在の農業改革において既得権益の強い抵抗に遭い、抜本的改革は実現せず、農業協同組合新聞からは「痛々しささえ感じる」と厳しい評価を受けています。
これらのネガティブな側面は、彼のリーダーシップに対する期待と対比される形で、今後の政策課題となるでしょう。
4. 小泉進次郎氏の総合的な政策方向性の推測

小泉進次郎氏の総合的な政策の方向性について、期待できる政策とリスクのある政策を先ほどの視点から簡潔に分析してみます。
☆期待できる政策領域
1. 環境・脱炭素政策:国際的な潮流を理解した先進的政策
2. デジタル化推進:若い世代の感覚を活かした行政改革
3. 既得権益改革:農協、官僚機構への改革圧力
4. 地方創生:都市と地方の新しい関係構築
△リスクのある政策領域
1. 外交・安全保障:経験と実績の不足
2. 財政・金融政策:専門性と深い理解の必要な分野
3. 社会保障制度改革:複雑な利害調整が必要な分野
※この記事はあくまでも筆者の憶測や推測です
まとめ(小泉進次郎氏の政治的可能性)
小泉進次郎氏は、改革志向と情報発信力という点で現在の政治不信の時代に求められる資質を持つ一方で、政策の深度や実現可能性において課題を抱えています。
それぞれに成功条件と失敗のリスクを持ち合わせていると言えます。
☆成功の条件
・優秀なブレーンチームの構築
・既得権益との対決における政治的根回し能力の向上
・発言の慎重さと政策の具体化
△失敗のリスク
・若さゆえの経験不足が重要局面で露呈
・メディア受けする発言と実質的政策のギャップ
・既得権益からの強い反発による政策頓挫
現在の日本政治の閉塞状況と国民の変化への期待を考慮すると、小泉進次郎氏には一定の可能性がありますが、慎重な準備と周囲の支援体制が成功の鍵となるのではないでしょうか?
ただ、小泉氏に限らず、現在の政権与党は誰が首相に就任しても、厳しい舵取りとなるでしょう。
| *参考元 | URLなど |
|---|---|
| Wikipedia | 小泉進次郎「ウィキペディア (Wikipedia): フリー百科事典」 |
| 環境省 | https://www.env.go.jp/annai/kaiken/r3/1001.html |
| president | https://president.jp/articles/-/81762?page=1 |
| awaihikari | https://awaihikari.media/report/entry-147.html |
| テレ朝 | https://news.tv-asahi.co.jp/news_economy/articles/000215415.html |
| 女性自身 | https://jisin.jp/domestic/1975039/ |
| 日経BOOKプラス | https://bookplus.nikkei.com/atcl/catalog/17/261450/ |
| JAcom | https://www.jacom.or.jp/kome/news/2025/06/250609-82331.php |
| Wikipedia | 田中角栄「ウィキペディア (Wikipedia): フリー百科事典」 |
| Wikipedia | 安倍晋三「ウィキペディア (Wikipedia): フリー百科事典」 |
| 小泉進次郎(公式サイト) | https://www.shinjiro.info/policy/ |
| ニッポン放送 | https://news.1242.com/article/406831 |
| 東洋経済 | https://toyokeizai.net/articles/-/880851?display=b |
| note | https://note.com/yoshiaki1973/n/n019b260ed0e8 |
| 日刊ゲンダイ | https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/373629#goog_rewarded |
| president | https://president.jp/articles/-/87443?page=1 |