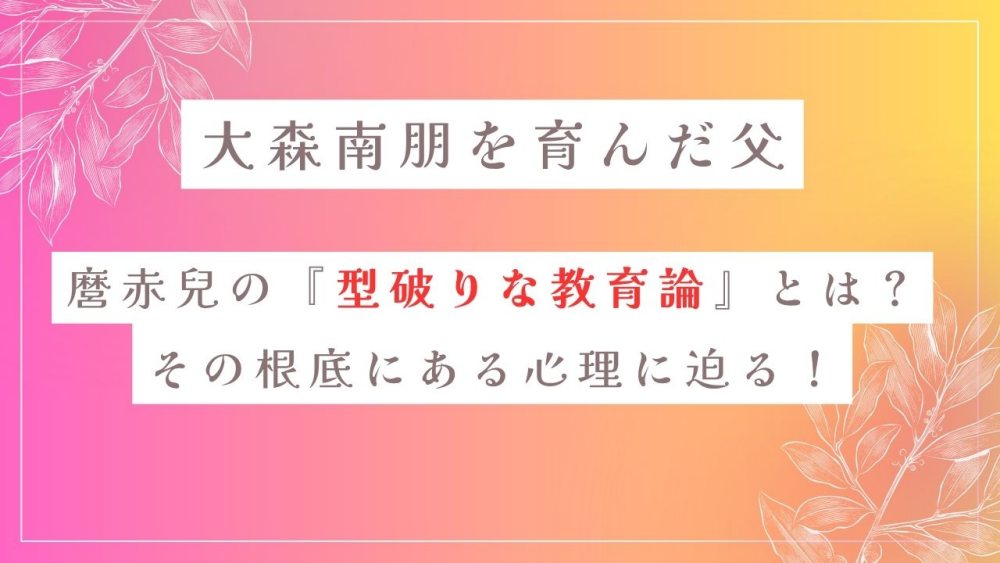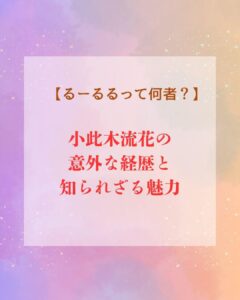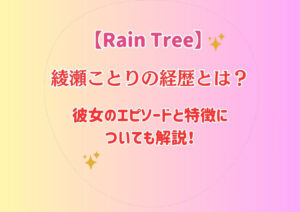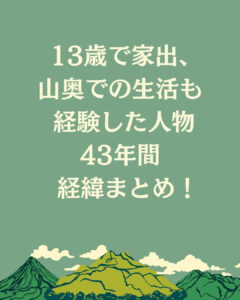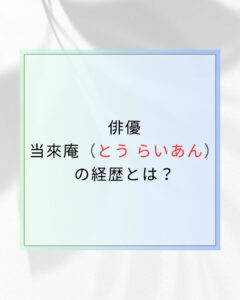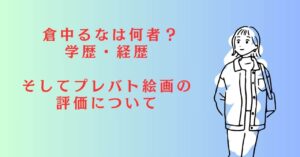7月9日放送「徹子の部屋」に、俳優の大森南朋(なお)さんが出演されています。
番組では、大森さんが子供のころに父 麿赤兒(まろ あかじ)さんの『頭に噛みつく』という型破りな教育論に対して、反面教師になったと語っているようです。
たまにしか会えなかったということで、一見は愛情の表れとも考えられますが、少し行き過ぎているようにも感じられるのではないでしょうか。
今回は、麿赤兒さんの『頭に噛みつく』という型破りな教育論から、その根底にある心理について調べてみました。
※心理については、あくまでも推測です
1. 麿赤兒さんの『頭に噛みつく』という教育論から見る心理?
この人達親子なの?選手権
— 坊主 (@bozu_108) June 4, 2025
金賞
大森南朋と麿赤兒 pic.twitter.com/WZx9XYD7ep
引用元/@bozu_108 Xより
麿赤兒さんの『頭に噛みつく』という型破りな教育論から見る心理について、以下の通りで進めていきます。
1. 自由奔放で型破りな個性
2. 芸術家肌気質の関心
3. 愛情表現のユニークさ
4. 内省的ではない可能性
1-1. 自由奔放で型破りな個性を持たせる
麿さんは、社会的な枠にとらわれず、自身の感性や本能に従って生きることを重視し、それを南朋さんに感情として伝えてのかもしれません。
伝統的な家庭像や父親像に縛られない、独自の価値観を持っているとも考えられるのではないでしょうか。
1-2. 芸術家肌気質の関心を持たせる
麿さんが舞踏家であることからも、身体表現や非日常的なものへの強い関心がうかがえます。
この「噛みつく」という行為も、ある種のパフォーマンスや表現の一環として捉えられていたのかもしれません。
この表現は、南朋さんに関心を持たせようと考えておられたのではないでしょうか。
麿さん自身は、舞踏家としてのキャリアを持ち、独自の表現方法を追求してきた方です。
彼は1972年に舞踏集団「大駱駝艦(だいらくだかん)」を設立し、身体表現を通じて人間の深層を探求してきました。
このような背景から、教育法も、創造性や自由な発想を重視するものであったとも考えられます。
因みに、舞踏集団には集団ユニットの「ゴールデンズ」というほぼ全裸で体中に金粉を塗って踊るショーもあり、この奇抜さが「噛みつく」という行為に影響があるのかもしれません。
1-3. 愛情表現のユニークさ
麿さんは、一般的な「優しい父親」とは異なる方法で愛情を示すタイプなのかもしれません。
直接的で時に過激な表現の中に、独特の愛情が込められていると本人は感じている可能性があります。
ただし、受け手であるお子さんにとっては、その愛情が伝わりにくかったり、戸惑いを感じさせたりすることもあるでしょう。
1-4. 内省的ではない可能性
これは、南朋さんの母親が夫(麿赤兒)の息子に接する教育を見て、『野生の王国的育て方』と語っているようです。
また、南朋さんの母親は勉強をしなくても、特に何も言わなかったと話しています。
そこから見える心理として、母や麿さんは、自身の教育法を深く反省したり、他者からの評価を気にしたりするタイプではないのかもしれません。
直感的で行動的な側面が強い傾向と言えるのではないでしょうか。
2. 麿赤兒さんの『頭に噛みつく』という教育論から見るポジティブな側面とリスク要因
麿赤兒さんの『頭に噛みつく』という教育論から見て、ポジティブな側面とリスク要因がありそうです。
それぞれの面について、簡潔に記載しておきます。
- 子供に強い印象と記憶を残す効果的な方法
- 愛情を身体で表現するストレートなコミュニケーション
- 創造性と個性を重視する前衛的教育観
- 社会的規範からの逸脱による子供の混乱
- 一般的な価値観との乖離による適応困難
- 過度な刺激による心理的負担の可能性
子どもの教育において、良い面と悪い面がありますが、麿赤兒さんの方針は南朋さんに影響を与え、自分は『まとも』に生きたいと思うようになったと番組では語っています。
番組では、具体的なことが語られているかもしれません。
※心理については、あくまでも推測です
| *参考元 |
|---|
| 大森南朋「ウィキペディア (Wikipedia): フリー百科事典」 |
| 麿赤兒「ウィキペディア (Wikipedia): フリー百科事典」 |
| 大駱駝艦「ウィキペディア (Wikipedia): フリー百科事典」 |
まとめ
大森南朋さんの父・麿赤兒さんの『型破りな教育論』から見る心理についてでした。
麿さんの教育法は、心理学的には非伝統的なアプローチと見なされるかもしれません。
彼の方法は、行動主義的な要素を含んでいると考えられます。
行動主義では、学習は刺激と反応の関係で成り立つとされ、子どもがどのように反応するかが重要視されます。
麿赤兒さんの「頭に噛みつく」という行動は、子どもに対する刺激として機能し、反応を引き出す手段だったのかもしれません。
しかし、リスク要因もあることから、子育てが慎重になる必要もあるでしょう。
大森南朋さんの場合は、「反面教師」として「まともに生きたい」と思うようになったことから、次の事に繋がったとも考えられます。
- 強烈な個性を持つ父親への複雑な感情を形成
- 社会的規範への憧れを生み出す
- 自分なりの価値観の確立を促進
- 芸術的感性の継承
(俳優として成功)
南朋さんにとって、父・麿さんの教育方法は結果として良かったと言えるのかもしれません。