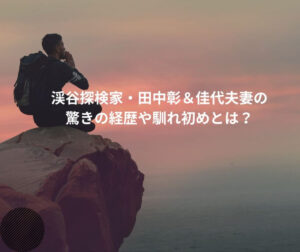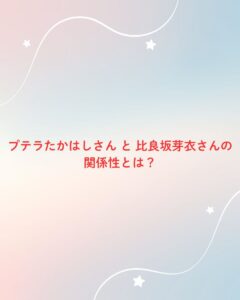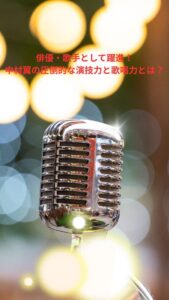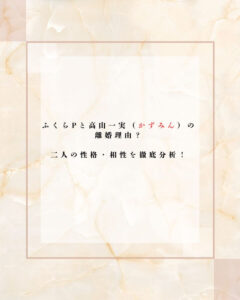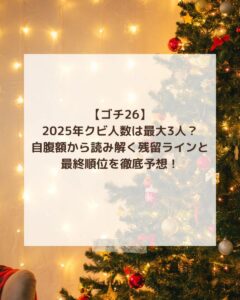9月10日放送の番組で、熊野古道の不思議なスポットについて取り上げられているようです。
その中の一部に「日本一大きなもの?」「入るのに緊張する場所?」「険しい道の先に卵のような巨大岩?」が紹介されています。
今回は、これらが何を指しているのかは存じませんが、憶測しながら調べてみました。
※番組内容と相違があるかもしれません

1. 熊野古道で日本一大きなものとは?
熊野古道で日本一大きなものとは、3つの候補がありそうです。
1. 大斎原(おおゆのはら)にある大鳥居
2. 日本最大の梛(ナギ)の木
3. 那智の滝
1-1. 大斎原(おおゆのはら)にある大鳥居
この大鳥居は、熊野本宮大社旧社地にあります。
引用元/Googleマップより
現在の熊野本宮大社から徒歩で10分ほどの場所にあるようです。
この大鳥居は、熊野古道を歩く際の重要なランドマークであり、訪れる人々にとっての象徴的な存在となっています。
熊野古道自体は、古来より続く巡礼の道であり、熊野三山(熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社)への参詣道としても知られています。
鳥居の特徴は、高さは約34メートル、幅は約42メートルで、日本一の大きさを誇るとされているようです。
大斎原は、かつて熊野本宮大社の旧社地であり、1889年の大洪水によって多くの社殿が流出した後、現在の熊野本宮大社が移転されました。
大鳥居はその名残として残っており、周囲の自然と相まって壮大な景観を形成しています。
遠くからでも目立つ存在で、訪れる人々に強い印象を与えているようです。
番組で、熊野古道で日本一大きいものとは、この大鳥居のことを指している可能性が高いかもしれません。
1-2. 日本最大の梛(ナギ)の木
熊野速玉大社にあるこの梛の木は、推定樹齢1000年であり、日本最大の梛の木として知られています。
樹齢1000年の梛の木がご神木。熊野三山のひとつ、熊野速玉大社。 pic.twitter.com/jqUPYyxiM8
— 和歌山県観光連盟 わかぱん【公式】 (@wakayamakanko) May 13, 2016
引用元/@wakayamakanko Xより
幹周りは約6メートル、樹高は約20メートルに達っするそうです。
この梛の木は、平安時代末期に熊野三山の造営奉行を務めた平重盛によって植えられたと伝えられています。
因みに、平重盛は平清盛の嫡男です。
梛の葉は、針葉樹でありながら広葉樹のような形状を持ち、特異な構造をしています。
葉には主脈がなく、縦に細い平行脈が多数存在し、横には簡単に裂けるが縦には裂けにくいという特性があるようです。
このため、男女の縁が切れないようにと、女性が葉を鏡の裏に入れる習俗もありました。
また、梛は熊野権現の象徴とされ、古来より道中の安全を祈るためにその葉を持ち帰る習慣があったそうです。
特に、梛の葉は魔除けの力があると信じられ、旅人たちはその葉を懐中に納めてお参りすることが一般的でした。
梛の木は天然記念物としても指定されており、その保護のために周囲は石柵で囲まれています。
訪れる人々は、その壮大さを目の当たりにすることができますから、熊野古道で日本一大きなものとして番組に紹介されている可能性もあるかもしれません。
1-3. 那智の滝
那智の滝は、和歌山県の熊野古道に位置する日本で最も高い滝であり、落差は133メートルに達します。

この滝は、熊野那智大社の別宮である飛瀧神社の御神体として崇められています。


那智の滝は日本三名瀑の一つに数えられ、国の名勝にも指定されているようです。
先ほど、記載したように落差は133メートル、幅は13メートルで、毎秒約1トンの水が流れ落ちています。
滝壺の深さは10メートル以上あり、滝の水は「延命長寿の水」としても知られているようです。
ここでは、滝を正面から見ることができる「御滝拝所舞台」が設けられており、ここからは滝の迫力を間近で感じることができます。
また、滝の水を飲むこともでき、訪れる人々にとっては特別な体験となります。
番組で言っていた『日本一大きなもの』は、日本一高い滝の落差(133メートル)を指している可能性が考えられます。
2. 熊野古道で入るのに緊張する場所とは?
熊野古道で入るのに緊張する場所とは、どこが該当するでしょうか?
番組が『緊張する場所』と表現した背景には、3つの可能性があると考えられます。
1. 精神的に緊張する場所?
2. 体力的に緊張する場所?
3. 物理的に危険が伴う場所?
細かく見れば、5つのことが考えられそうです。
それぞれについて見ていきましょう。
※これはあくまでも筆者の推測です
2-1. 精神的に緊張する場所とは?
精神的に緊張する場所として、大雲取越(おおぐもとりごえ)があります。
大雲取越の舟見峠と色川辻の間にある谷道には、「亡者の出会い」と呼ばれる伝説があるようです。
妙法山阿弥陀寺:和歌山県東牟婁郡那智勝浦町南平野2270-1
— 無用ノ介 (@muyonosuke) April 4, 2019
「亡者の熊野参り」を象徴する古刹。ひとつ鐘を撞いて血脈をいただき、樒山とも呼ばれる妙法山頂上の浄土堂まで古道を辿る。大雲取越・小雲取越は亡くなった縁者に出会う、ダルという妖怪にとりつかれるという。https://t.co/6MmtpyR0zT pic.twitter.com/hHIBFsPore
引用元/@muyonosuke Xより
この道は、細い杉並木に挟まれた石畳の区間で、歩いていると亡くなった友人や肉親に出会うことがあるとされています。
伝説によると、旅人がこの道を歩いていると、向かい側からやってくる亡くなった人に出会うことがあるとされているようです。
出会った後、家に帰るとその人が既に亡くなっていたことを知るという逸話も残っているようですね。
熊野は、イザナミノミコトが埋葬された場所とされ、死者の国「黄泉」との関連が強い地域です。
このため、山道はこの世とあの世の境界が曖昧になる場所と考えられ、古くから人々に畏敬の念を抱かせてきました。
このような伝説は、旅人に精神的な緊張感を与える要因となっているようです。
熊野は古来から死後の世界と深く関連付けられており、特にこの地域は神秘的な雰囲気を持っています。
熊野古道を歩くこと自体が、肉体的な挑戦でもありますが、精神的な修行の場とも見なされています。
もし番組が精神的な緊張を伴う場所を指しているのなら、それは大雲取越の舟見峠と色川辻の間にある谷道のことかもしれません。
2.-2. 体力的に緊張する場所とは?
番組が体力を消耗する場所を指しているとしたら、その理由として3つの可能性が考えられます。
・鹿ヶ瀬峠
・八鬼山越え
・大雲取・小雲取越
鹿ヶ瀬峠は、熊野古道の紀伊路で最大の難所とされており、急峻な山越えが特徴です。
藤原定家がその険しさを「崔巍の嶮岨」と称したほどであり、長さ503mの石畳道が続くため、歩く人にとっては相当な苦痛となるでしょう。
八鬼山越えは、熊野古道伊勢路の中で最も標高が高く、登り・下りともに厳しい道です。
特に「七曲がり」と呼ばれる急な上り坂が続き、体力を大いに消耗します。
約10kmにわたるその道は、石畳が続く上に、かつては山賊や狼が出没していたため、巡礼者にとっては非常に過酷な道だったと言えるでしょう。
大雲取・小雲取越は、大雲取越は熊野古道の中でも最大の難所とされ、急な石階段や厳しいアップダウンが続きます。
亡くなった親しい人に出会えるという逸話のある”亡者の出会い"。
— 風景写真家 高橋智裕 (@tomotakaenter) February 5, 2020
古人は様々な想いを胸に命がけでこの険しい古道を歩いていたのですね。
あなたにはもう一度会いたい故人はいらっしゃいますか。
亡くなるのは当たり前なのだけれど、別れが永遠に来なければいいのにと思ってしまう。
熊野古道大雲取越 pic.twitter.com/gZn8iFPqAl
引用元/@tomotakaenter Xより
特に大雲取越は硬い火成岩でできた急な山を越えるため、体力的に非常に厳しいとされているようです。
小雲取越は、大雲取越よりは、やや緩やかと言えるでしょう。
大雲取越は、先ほど精神的に緊張する場所として「亡者の出会い」の伝説でも触れました。
2-3. 物理的に危険が伴う場所とは?
熊野古道で、入るのに物理的に危険が伴う場所としては、二河峠付近(大辺路街道)が該当しそうです。
悪戦苦闘。熊野古道大辺路の街道マップにない本当の区間はこんな感じ。なぜルート指定してないのか理由がわかる。でも満足! pic.twitter.com/tGFsUZ80IV
— にゃおすけ (@yaonyaosuke2) January 4, 2019
引用元/@yaonyaosuke2 Xより
二河峠付近(大辺路街道)には、物理的に危険が伴う特徴がいくつかあります。
二河峠周辺の道は非常に狭く、特に急な斜面が続いており、このため、足を滑らせると大けがにつながる危険性があります。
周囲には樹木が少ないため、滑落した場合のクッションがなく、転落のリスクが高まり、特に雨天時には道が滑りやすくなるため、注意が必要です。
二河峠は急な高低差が特徴で、登り下りが体力的にも厳しい部分があります。
以上が、熊野古道に入るのに緊張する場所の3つについてです。
番組が「緊張する場所」と表現したのは、挙げた3つのうち、いずれかを指しているのかもしれません。
3. 熊野古道で険しい道の先にある卵のような巨大岩とは?
熊野古道で険しい道の先にある卵のような巨大岩と呼べるものはいくつか該当しそうです。
以下の3つが考えされます。
1. 丹倉神社の鳥居下の磐座(いわくら)
2. 神倉神社の近くのゴトビキ岩
3. 大雲取越の道沿いの丸い石
それぞれについて触れます。
3-1. 丹倉神社の鳥居下の磐座(いわくら)
丹倉神社(あかぐらじんじゃ)の鳥居を抜けて下に降りると、目の前に現れるのは巨大な岩が現れます。
引用元/Googleマップより
〒519-4446 三重県熊野市育生町赤倉
⛩丹倉神社(三重県熊野市)
— 狭野の人 (@patmjgdw7294385) August 19, 2025
社殿はなくご神体の磐座のみの神社です。 pic.twitter.com/DaaKkIdq8U
引用元/@patmjgdw7294385 Xより
これは、この神社のご神体である「磐座(いわくら)」と呼ばれる岩です。
この岩は、古代からの自然崇拝の象徴であり、特に「磐座信仰」として知られています。
丹倉神社は、社殿を持たず、直接この巨岩を拝む形式の神社です。
この岩は、神々が宿る場所とされ、信仰の対象となっています。
3-2. 神倉神社の近くのゴトビキ岩
熊野古道で神倉神社の近くに位置する「ゴトビキ岩」は、卵のような巨大岩と言えるかもしれません。
🏔ゴトビキ岩(和歌山県新宮市)
— 狭野の人 (@patmjgdw7294385) July 28, 2025
熊野権現降臨地。 pic.twitter.com/hE4VfVzH67
引用元/@patmjgdw7294385 Xより
所在地: 〒647-0081 和歌山県新宮市神倉 1丁目13−8
高さは、約100メートルの断崖絶壁に鎮座しています。
卵のような感じにも見えますが、形状はヒキガエルのようであることから、地元の方言で「ゴトビキ」と名付けられたようです。
ゴトビキ岩は、日本創生の時代に神武天皇を救った神様が宿る岩とされており、地域の信仰の対象となっています。
3-3. 大雲取越の道沿いの丸い石
他にも、ゴトビキ岩ほど巨大とは言えないかもしれませんが、大雲取越の道沿いに「丸い石」が たくさんあるようです。
「たまご石」とも呼ばれており、緑の苔に覆われたものがあります。
石と呼ぶか、岩と呼ぶかは人それぞれだと思いますが?
世界遺産「熊野古道」の難所として知られる大雲取越の道沿いに鎮座する「円座石」の前面を覆っていたコケがほぼなくなっていることがわかりました。人為的にはぎ取られた可能性が高いようです。http://t.co/gcslsubO5e pic.twitter.com/NNDVmI3cNf
— 産経ニュース (@Sankei_news) May 4, 2015
引用元/@Sankei_news Xより
小さな石もあれば、大きな石や岩のようなものもありますし、神倉神社に向かうと同様に険しい道ですから、大雲取越の道沿いにある「丸い石」を番組で取り上げている可能性もあるかもしれません。

| *参考元 | URLなど |
|---|---|
| Wikipedia | 鹿ヶ瀬峠「ウィキペディア (Wikipedia): フリー百科事典」 |
| Wikipedia | 雲取越え鹿ヶ瀬峠「ウィキペディア (Wikipedia): フリー百科事典」 |
| Wikipedia | 熊野古道「ウィキペディア (Wikipedia): フリー百科事典」 |
| 好日山荘 | https://www.kojitusanso.jp/tozan-report/detail/?fm=2106 |
| 三重県立古道センター | https://www.kumanokodocenter.com/kodoinfo/kodo10.html |
| 熊野本宮 | https://www.hongu.jp/kumanokodo/hongu-taisya/ooyunohara/ |
| 那智の滝 | https://kumanonachitaisha.or.jp/pavilion/waterfall/ |
| 南紀熊野ジオパーク | https://nankikumanogeo.jp/geosite/kamikurasan-no-gotobikiiwa/ |
| MBSコラム | https://www.mbs.jp/mbs-column/maetoato/archive/2019/09/21/018436.shtml |
| エキサイトブログ | https://wakigaaris.exblog.jp/27573809/ |
| AGARA | https://www.agara.co.jp/article/93387 |
| わかやま歴史物語 | https://wakayama-rekishi100.jp/story/097.html |
まとめ
熊野古道の一部の不思議なスポットで、「日本一大きなもの?」「入るのに緊張する場所?」「険しい道の先に卵のような巨大岩?」など、番組で取り上げられていることについて、憶測しながら調べました。
- 大斎原(おおゆのはら)の大鳥居
- 日本最大の梛(ナギ)の木
- 那智の滝
日本一大きなものですから、言葉通りであれば、大斎原の大鳥居か、梛の木のどちらかが該当しそうです。
1. 精神的に緊張する場所?
大雲取越の舟見峠と色川辻の間にある谷道
2. 体力的に緊張する場所?
・鹿ヶ瀬峠
・八鬼山越え
・大雲取・小雲取越
3. 物理的に危険が伴う場所?
二河峠付近(大辺路街道)
番組で取り上げるとすれば、精神的に緊張する場所か、物理的に危険が伴う場所が該当するのではないでしょうか?
大雲取越の舟見峠と色川辻の間にある谷道か、二河峠付近(大辺路街道)が該当しそうな気がしますが、番組のこの「緊張する場所」が何を指しているのかは確認してみないとわからないですね。
1. 丹倉神社の鳥居下の磐座(いわくら)
2. 神倉神社の近くのゴトビキ岩
3. 大雲取越の道沿いの丸い石
(たまご石とも呼ばれる)
言葉通りで解釈するのであれば、「磐座」か、「ゴトビキ岩」のどちらかを番組で取り上げているのではないでしょうか?
以上が、憶測でまとめたものです。
※番組内容と相違があるかもしれません