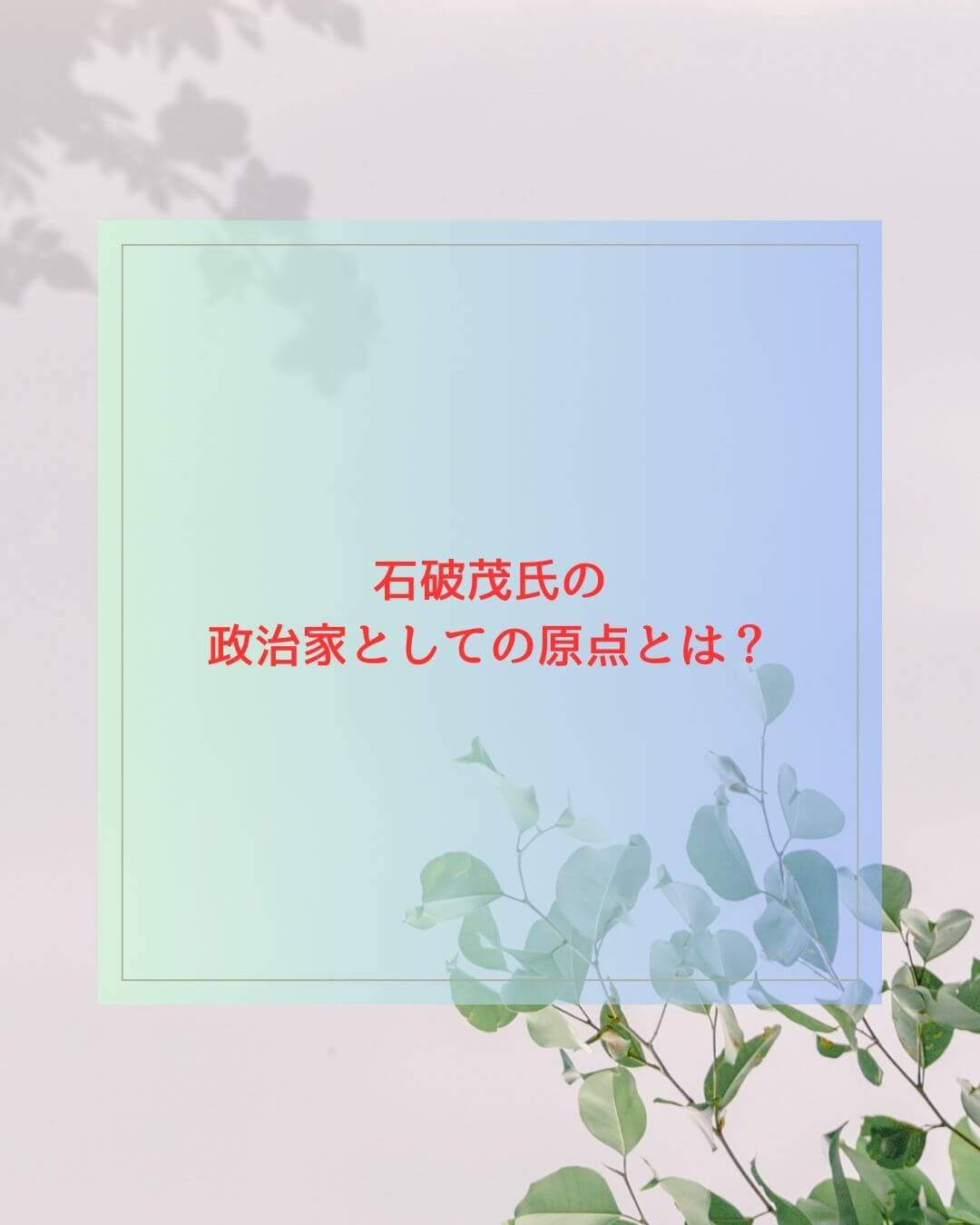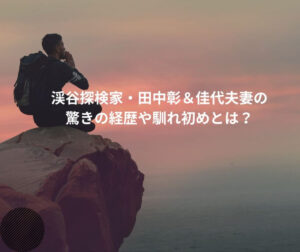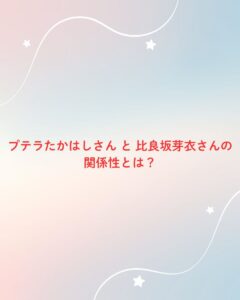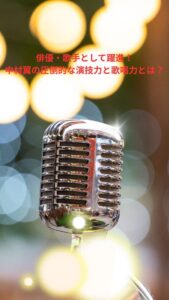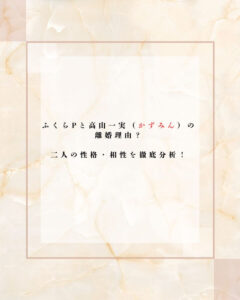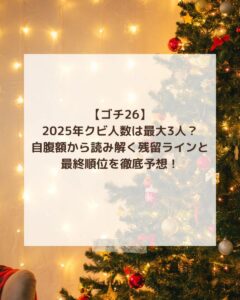石破茂氏の政治家としての原点は、彼の家族の背景に深く根ざしています。
彼の父、石破二朗氏は鳥取県知事を務めた政治家であり、祖父の石破市造(いしば いちぞう)氏は農家出身で村長を務めた人物です。
このような家系は、石破氏の政治的信念や活動に大きな影響を与えています。
今回は、石破氏の政治家としての原点で影響を与えた親族や大物政治家などについて触れていきます。
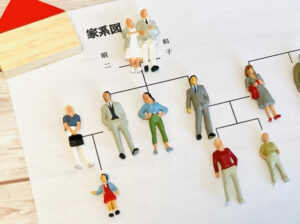
1. 石破茂氏の家族ルーツについて
石破茂の家系図 pic.twitter.com/iFkJIZnd1F
— 🇫🇷パリババ (@SATOROTUS) July 8, 2025
引用元/@SATOROTUS Xより
石破茂氏の家族ルーツについて、3人の親族を取り上げます。
1. 父親・石破二朗氏
2. 祖父・石破市造氏
3. 母方の祖父・金森太郎氏
1-1. 父親・石破二朗氏について
石破茂氏のお父様である故石破二朗氏は鳥取県知事としてご活躍され鳥取中央郵便局の前に銅像が鎮座されています。
— 金融ごりごり営業女🦍 (@KLJ6EEVPabBaMT8) August 31, 2020
御子息である石破茂氏の銅像もとても見てみたい気はしますが難しいかもしれませんね。 pic.twitter.com/D9bLGTzqdF
引用元/@KLJ6EEVPabBaMT8 Xより
- 出身:鳥取県八頭郡大御門村
(現在の八頭町) - 経歴: 東京帝国大学法学部卒業
建設省官僚
鳥取県知事
(1958~1974年、16年間4期)
参議院議員
(1974年7月~1981年9月)
自治大臣
(1980年7月~12月) - 功績:鳥取県の発展に大きく貢献し、「道路の神様」と呼ばれ、鳥取駅付近に銅像が建てられている
石破二朗氏は1908年(明治41年)に鳥取県の貧しい農家に生まれました。
彼は幼少期から勉学に励み、東京帝国大学法学部を卒業後、内務省に入省し官僚としてのキャリアをスタートさせています。
戦後、彼は内務省でキャリアを積みつつ政治家としての道を歩み始めます。
1958年には、鳥取県知事に当選し、1958年から1974年までその職を務めました。
知事としては、農業振興や教育の充実、インフラ整備に尽力し、県民からの信頼を得ていました。
1974年2月には、鳥取県知事を辞任し、同年7月に行われた参議院議員で当選します。
以来、自民党で要職を歴任し、自治大臣まで務めました。
二朗氏の人柄は、清貧と努力の人であり、故郷に愛着も持ち、義理人情に厚い人物であるようです。
また、農本思想をもち、儒教精神に裏打ちされたその人柄は、質実剛健で清廉潔白だと評価されています。
鳥取県では、その多大な功績から、二朗氏の銅像が建っているほどです。
1-2. 祖父・石破市造氏について
- 職業:農家出身
- 政治経歴:鳥取県八頭郡大御門村の村長を務めた
- 背景:代々農業を営む家系で、地域の小さな村(大御門村)の村長として地域に貢献
石破市造氏は、1874年(明治7年)に鳥取県八東郡大御門村大字殿(現在の八頭町)で生まれました。
彼は農家出身でありながら村長を務めた人物で、地域社会に根ざしたリーダーシップを発揮しています。
20歳の頃には村役場に勤めており、34歳頃に大御門の村長に就任しました。
また、若い頃には山を開拓して「二十世紀梨」「御所柿(ごしょがき)」などを栽培しつつ、養蚕もされていたようですが、どれも成功とまではいかなかったようです。
市造氏は、この成功とまではいかなかった経緯を自身が十分な学校教育を受けていなかったと振り返ったようです。
彼は高等小学校を卒業後、家業の農業に従事していました。
つまり、市造氏は高等小学校を卒業した学歴しかないということになります。
ただ、明治時代は農業技術が進歩していなかったこともあり、一概に当時の学識で農業栽培が上手くいくとは限らないかもしれません。
彼は自身が十分な学校教育を受けていなかったとの自覚からか、子供たちの教育には熱心な子煩悩となっていました。
市造氏は、自身も英語講師が話した内容を筆記し、講義録として勉強していたようです。
この熱心な勉強に取り組んだ結果が、やがて政治の道への歩みとなったのかもしれません。
1-3. 母方の祖父・金森太郎氏について
石破茂氏の母方の祖父 金森太郎(かなもり たろう)氏についても触れておきます。
- 第25代 山形県知事
(1934~1936年) - 経歴: 東京帝国大学法科大学卒業
大阪府警部長
徳島県知事
山形県知事
東北興業副総裁
樺太開発副総裁
- 血筋:父は宗教家・金森通倫
(熊本バンドのメンバー)
石破茂氏の母(和子氏)は、金森太郎氏を父に持ちます。
金森太郎氏は1888年(明治21年)に生まれ、内務省に入省した後、官僚としてのキャリアを築き、1933年から1934年まで徳島県知事を務め、その後に1934年から1936年まで山形県知事を務めました。
この短期間でなぜ徳島県知事や山形県知事を務めたのかの経緯は不明です。
知事職を退いた後は、東北興業の副総裁や樺太開発の副総裁を歴任しています。
一部では東北パルプ副社長や東北船渠の社長に就任したのではないかとの情報もあるようです。
金森太郎氏は、父親が金森通倫(かなもり みちとも)氏という著名な牧師であり、教育や公共サービスに対する強い信念を持っていたことが知られています。
彼の家族は政治や教育の分野で影響力を持つ人物が多く、金森太郎氏自身もその伝統を受け継いでいます。
因みに、熊本バンドの金森通倫は2013年の大河ドラマ『八重の桜』に俳優の柄本時生さんが演じていたのでご存知な方も多いのではないでしょうか?
2. 石破茂氏の政治家としての原点について
皆さま今回の自民党総裁選、本当にありがとうございました。いつの日か、国民の皆さまのために、日本国のために、次の時代のために。皆さんのお気持ちに報いることができるよう、石破茂、全力を尽くしてまいります。どうもありがとうございました。 #納得と共感 pic.twitter.com/RpHnPujUIJ
— 石破茂 (@shigeruishiba) September 14, 2020
引用元/@shigeruishiba Xより
石破茂氏の政治家としての原点については、父・祖父、そして田中角栄元首相の影響があると言えます。
それぞれについて触れます。
2-1. 父・石破二朗氏の影響
石破茂氏は、政治について父の二朗氏から次のように言われています。
二朗氏は息子に向けて『政治家はお前みたいに人のいい奴に務まる仕事ではない』と言われ、当初 茂氏は政治家になるつもりはなかったそうです。
二朗氏は息子に向けて『人のいい奴』と言っていますから、当時の茂氏は根が正直だったのかもしれません。
そんな息子が政治に携わることの力量を危ぶんでいたとも読めるのではないでしょうか?
しかし、茂氏は父親の政治に対する姿勢や地域への貢献を間近で見て育ったことから、政治に興味を持つきっかけにはなったと考えられます。
茂氏は父 二朗氏が亡くなる以前は、三井住友銀行(旧・三井銀行)に勤務しており、父の後を継ぐかは躊躇していたかもしれませんが、ある大物政治家の後押しから政治に身を置くことになります。
2-2. 祖父・石破市造氏の影響
農家出身から村長になった祖父・市造氏の姿は、地域に根ざした政治の重要性を示していますが、その経緯が孫の茂氏に直に伝わることはなかったでしょう。
おそらく、祖父の市造氏については父の二朗氏から聞かされていると思われます。
そもそも石破茂氏は、祖父の市造氏に会ったことは一度もありません。
茂氏が生まれた頃は、祖父の市造氏は既に亡くなっていました。
祖父の市造氏が亡くなったのは、1941年(昭和16年)で茂氏が生まれたのは1957年(昭和32年)ですから、祖父が亡くなって16年後に誕生したということになります。
父の二朗氏が49歳の頃に生まれた子供ですから、生きている頃の祖父に会えなかったのも無理もないですね。
ただ、祖父の経緯は父の二朗氏から聞かされていると思われることから、石破茂氏の地方創生への関心や農業政策への理解の原点になったと考えられます。
2-3. 田中角栄氏の影響

石破茂氏は、田中角栄氏との出会いが政治への転機となっています。
父の二朗氏が1981年に死去し、二朗氏と友人関係の田中角栄氏が葬儀委員長を務めました。
茂氏は、葬儀のお礼を伝えるため田中氏の私邸を訪問し、田中氏から『君が選挙に出るんだ』と強く背中を押されます。
当時の茂氏は24歳で父が参議院議員であり、まだ規定の30歳ではないことから、直ぐに選挙に出られるわけではないと考えていたようです。
しかし、田中氏は『誰が参議院に出ろと言った、衆議院だ!』と机を叩きつけて説得し、半ば強引に茂氏は政界入りを決断しています。
茂氏は父の死後、政治家になるかどうか躊躇していた時期もありました。
それを見越した田中氏は、未来の日本のために茂氏の才能が必要だと考え、強く後押しをしたのかもしれません。
茂氏は田中氏から選挙区を一軒一軒を歩き回る基本を叩きこまれ、ドブ板選挙の徹底指導を受けています。
また、アメリカとの対等な政治姿勢で田中氏の「対米自立」の考え方を継承しているとも見られているようです。
これらの経緯から茂氏にとって田中角栄氏は、単なる政治の師ではなく、政治家としての生き方や哲学を教えた「もう一人の父」と表現されることがよくあります。
田中角栄氏との出会いが無ければ、石破茂氏は政治家としての道を歩んでいなかったかもしれません。
| *参考元 | URLなど |
|---|---|
| Wikipedia | 石破茂「ウィキペディア (Wikipedia): フリー百科事典」 |
| Wikipedia | 石破二朗「ウィキペディア (Wikipedia): フリー百科事典」 |
| Wikipedia | 石破市造「ウィキペディア (Wikipedia): フリー百科事典」 |
| Wikipedia | 金森太郎「ウィキペディア (Wikipedia): フリー百科事典」 |
| レファレンス協同データベース | https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?page=ref_view&id=1000032696 |
| AERA | https://dot.asahi.com/articles/-/239534?page=3 |
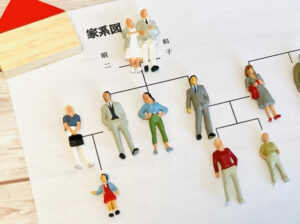
まとめ(石破茂氏の政治家としての原点)
- 家族の政治的遺伝子:父方・母方ともに政治・行政に携わる家系
- 地域への愛着:祖父の村長経験や父から学んだ地域密着型政治
- 田中角栄氏からの政治指導:選挙の基本であるドブ板選挙の徹底指導
- 対等な政治姿勢:田中角栄氏の「対米自立」の考え方を継承
石破茂氏は1986年の衆院選で29歳という全国最年少で初当選を果たし、田中角栄氏から学んだ「一軒一軒回る」選挙手法で5万4千軒を訪問して当選を勝ち取りました。
これらの経緯から、石破茂氏の政治家としての原点は、農家出身の祖父から県知事まで務めた父親という政治的血筋と、田中角栄氏との運命的な出会いが組み合わさって形成されたと言えるのではないでしょうか。
ただ、現在 総理大臣に就任してからは客観的な目線で見て、総理大臣という椅子や政権に固執しているとも、見えなくはありません。
父や祖父の教訓が活かされると良いですね。