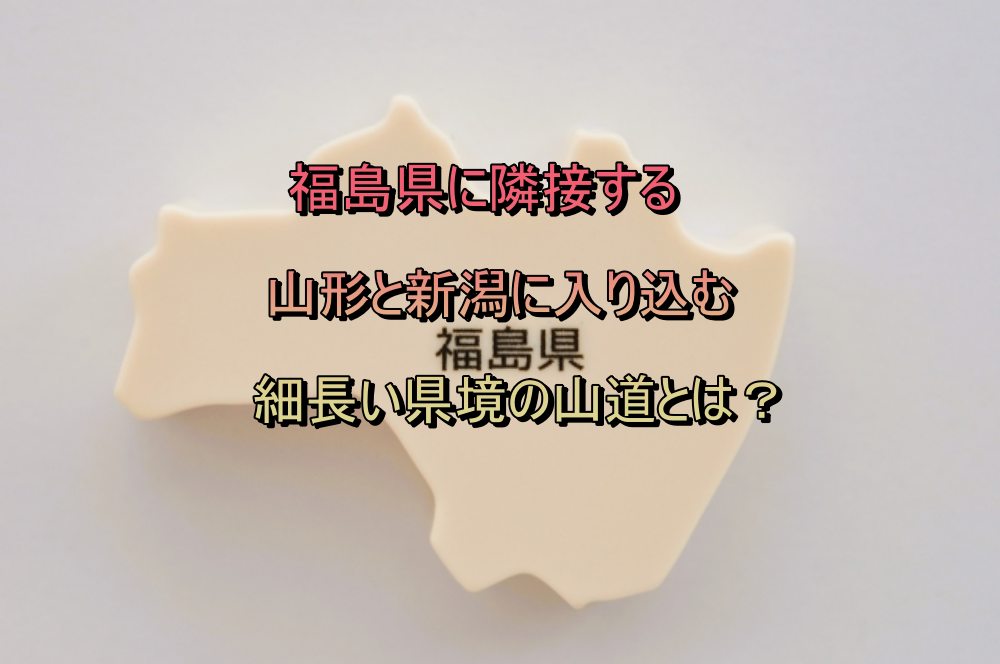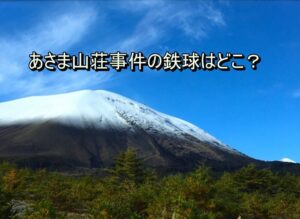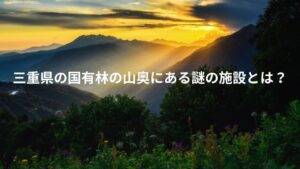11月5日放送の番組で、福島県に隣接する山形と新潟に入り込む細長い県境について紹介されています。
勘違いしやすいのは、この細長い県境を山形県か新潟県と思う人が大半ではないでしょうか。
この細長い県境は福島県に属します。
番組にあるように、なぜこんな形になったのかの経緯について簡単に触れます。
ただ、この福島県の細長い県境は2020年に放送していた「林先生の初耳学」でも触れられていたので、ご存知な方もおられるかもしれせん。
※番組内容と相違があるかもしれません

福島県に隣接する県境が細長くなった経緯について
番組内の地図にもありましたが、山形と新潟に入り込む、赤く表示された細長い県境は、福島県に属します。
福島県の細長い県境が形成された背景には、歴史的な領土争いと地域の文化的な重要性が関係しているようです。
この県境は、福島県が新潟県と山形県の間に食い込む形で延びており、特に飯豊山(いいでさん)の周辺に位置しています。
飯豊山は福島県にあり、住所は喜多方市山都町一ノ木となっています。
この不思議な県境は、三国岳(さんごくがく)から御西岳(おにしだけ)まで約7~8kmにわたって延びており、最も狭いところで幅約50~90cmという驚異的な細さです。
なぜ、このような形になったのかは、以下の通りです。
1. 廃藩置県による混乱
2. 福島県民の猛烈な反対運動
3. 妥協案としての細長い県境
それぞれについて触れます。
1-1. 廃藩置県による混乱
山形・新潟「なんで飯豊山の山頂は福島なんだ!この県境、ねじ込みすぎだろ!」
— RAY (@akrfld) January 4, 2024
福島「飯豊山神社の麓宮は福島県にあるから、山頂の奥宮と参道も福島のもの!」
山形・新潟「なんだそりゃ!」 pic.twitter.com/4HsaJUoYjX
1886年(明治19年)頃の明治時代の廃藩置県により、もともと会津藩の領地だった東蒲原郡が福島県から新潟県に編入されることになった経緯があります。
当時、福島県庁の所在地をめぐる争いがあり、政府が県北西部の東蒲原郡を新潟県に編入することで、県庁移転の動きを抑え込んだという政治的背景もあったようです。
この結果、飯豊山の山頂とその神社が新潟県に属することとなり、福島県の一ノ木村(現・喜多方市)は強く反発しました。
1-2. 福島県民の猛烈な反対運動
先ほども記載したように、神社が新潟県に属することに対して、特に飯豊山神社(いいでさんじんじゃ)を信仰する人々が猛烈に反対しました。
福島にあるこのニョロニョロは廃藩置県で地図にある飯豊山が新潟県に編入された時に飯豊山神社とその信仰者が「あれはウチのもんだ」って反対運動を起こして無理矢理山頂の神社と参道を福島県にしたから出来た変わった県境
— 植田白水(鶴見甘草) (@spring_asdurawa) March 2, 2018
実際の参道の幅は1mくらいしかないから福島県を股の間に収めることができるゾ pic.twitter.com/KFvnUeoCJz

その反対した経緯は、飯豊山神社は福島県喜多方市に麓宮を置く古くからの信仰の山であり、福島県民にとって神聖な場所であり、古来より参拝が行われていたからです。
五穀豊穣を祈願するための重要な山とされており、この山は「日本百名山」の一つにも選ばれ、登山は地域の伝統行事としても位置づけられています。
江戸時代の絵巻物にも、飯豊山神社に詣でる人々の姿が描かれています。
また、会津藩の時代から、喜多方市の一ノ木村(現在の山都町)が参道を整備し、管理してきたのも理由の一つです。
1-3. 妥協案としての細長い県境
約20年に及ぶ領有権争いの末、最終的に妥協案として以下のような決着となっています。
- 飯豊山神社の参道(登山道)とその周辺のみを福島県の領域とする
- 飯豊山神社の境内が御西岳頂上付近まで続いていたという歴史的根拠に基づき、御西岳山頂まで福島県境とする
- 結果として、尾根をつたう細い登山道だけが福島県となった
約20年後の1907年(明治40年)、政府は飯豊山の登山道とその周辺を福島県に認める裁定を下しました。
この県境や飯豊山の登山道について、YouTubeで配信されている方もおられるので、興味のある方は視聴してみてはいかがでしょうか。
| *参考元 | URL |
|---|---|
| @nidonesuishou・チャンネル | https://youtube.com/shorts/Eh8iIf8zeDc?si=sOTsv2nyGBGZdrJA |
| @山と神社チャンネル・チャンネル | https://youtu.be/1fFaeoE3x6A?si=rf5qrLyOVeua-CQ- |
| MBSコラム | https://www.mbs.jp/mbs-column/mimi/archive/2020/07/23/020758.shtml |
| japaaan | https://mag.japaaan.com/archives/221204 |
| 日本経済新聞 | https://www.nikkei.com/article/DGXMZO65205650Q0A021C2910E00/ |
| 山と溪谷オンライン | https://www.yamakei-online.com/yamanavi/yama_area.php?id=108 |

まとめ
番組で紹介された福島県の細長い県境についてでした。
この細長い県境は、現在も以下のような特徴を持っています。
- 所在地:福島県喜多方市山都町
- 長さ:三国岳から御西岳まで約7~8km
- 幅:最も狭いところで約50cm、通常90cm程度
- 標高:約2,000m級の険しい山岳地帯
- 登山道の右側が山形県、左側が新潟県
この奇妙な県境は、明治時代の行政区画変更に対する地域住民の信仰心と郷土愛が生み出した歴史的遺産と言えます。
単なる行政上の線引きではなく、そこには福島県民の飯豊山に対する深い思いが込められていると言えるでしょう。